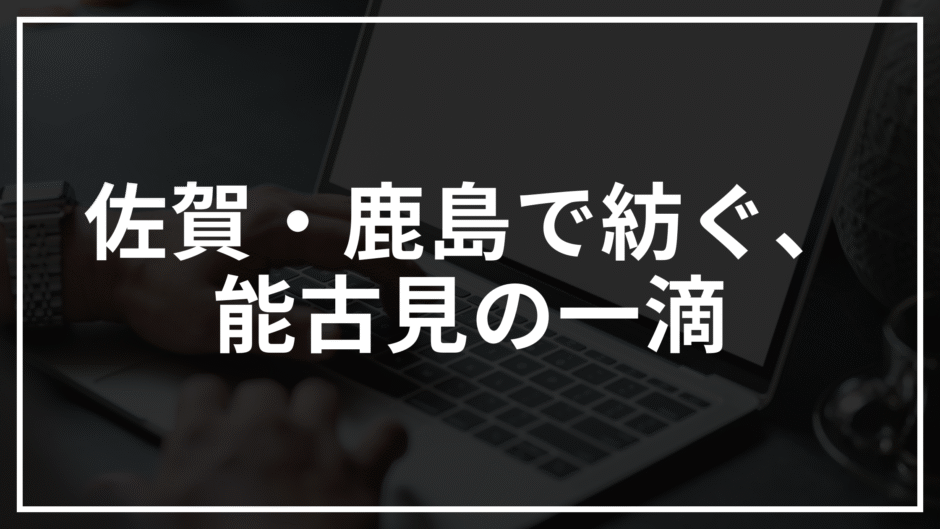佐賀県鹿島市能古見(のごみ)。
清らかな水と豊かな大地に囲まれたこの地で、馬場酒造場は200年以上ものあいだ、地元とともに歩み続けてきました。
酒造りは、まず「自然との対話」から始まります。
梅雨入り直前の6月。田植えとともに、物語の第一章が幕を開けます。
人々の手で丁寧に植えられた酒米は、雨と陽の光を浴びながら夏を越え、秋に向けて少しずつ熟していきます。
「舞台の幕は、大地から」。
その言葉の通り、能古見という名酒は、土地と人との深い関わりのなかで育まれています。
気候変動や高齢化の影響で、年々難しくなる酒米の栽培。
それでも馬場酒造場は、地元の農家と力を合わせ、「できる限り地元産の米だけで造る」姿勢を守り続けています。
秋、稲穂が黄金色に輝きはじめる頃。
一粒一粒、ていねいに刈り取られた米が酒蔵へと運ばれ、ここから本格的な酒造りが始まります。
10月から12月にかけては、「米を洗い、蒸し、麹を育てる」という表現力を養う工程──まるで役者が本番に向けて稽古を積むような、緊張感と集中力の時間です。
静かな寒さに包まれた1月、酒蔵では「発酵」という目に見えない命との対話が始まります。
麹から引き出した酵素と、水・米が一体となり、酵母の活動によってアルコールへと変わっていく——この過程は、まるで台本のない舞台劇。人の手で温度や湿度を微細に調整しながら、酵母の“声”を聴くように酒造りが進みます。
馬場酒造場では、酵母の育成すら自家製にこだわり、「この一本にしかない表情」を持つ酒を目指しています。
温度変化わずか0.1度単位の世界。そのなかで酵母が穏やかに、しかし確かに働く時間は、酒の“性格”を決定づける最も繊細な瞬間です。
2月に入ると、約30日かけて発酵した醪(もろみ)を丁寧に搾り、瓶詰めへ。
搾りたての一滴が空気にふれ、ふわりと立ちのぼる香りは、まさに物語の最終章。
それはまるで、織り上げた舞台のフィナーレにふさわしい、華やかで透明感のある余韻です。
能古見の酒は、ただの日本酒ではありません。
それは、四季折々の自然と、人の手間と、時間の積み重ねが生んだ“物語そのもの”です。
口に含んだ瞬間、ふわりと広がる米の旨み。
香りに漂う、蔵の空気と職人の気配。
そして、喉を通ったあとのやさしい余韻は、まるで舞台の幕が下りたあとの静寂のようです。
たとえば、夜の静かな時間に、あたたかい照明の下でグラスを傾けるとき。
そこには酒以上の何かがあります。
能古見の1本が、「今日までの時間」や「これからの物語」に、静かに寄り添ってくれるのです。
特に注目したいのは、能古見が“飲む人の心の状態”によっても表情を変えるということ。
疲れた日にはふくよかな甘さが、嬉しい日にはキリリとした清らかさが立つ——
そんな不思議な“対話性”も、能古見の魅力の一つです。

能古見の味わいは、まさに「柔らかさと深みの共存」。
派手な香りで主張するのではなく、飲み手の感情や時間の流れにそっと寄り添ってくれるのが特徴です。
- 香り:炊きたての米のような、やさしい香り。果実のような甘やかさも時折顔を出す。
- 口当たり:滑らかで柔らかく、雑味が少ない。水の良さと、丁寧な仕込みが伝わる。
- 味の芯:しっかりとした米の旨味が真ん中にあり、飲むたびにじわりと広がる余韻。
- 飲みごろ:冷やでも燗でも良いが、特に“ぬる燗”で深みが引き立つ。
「いつの間にか空いていた」そんなタイプのお酒。飲み手の時間を吸い込み、そっと心に余韻を残すような、懐の深い一本です。
公式情報はこちら(馬場酒造)から確認できます。
能古見という酒には、四季の営みと、土地に根ざした人々の手仕事、そして飲む人の人生さえも溶け込んでいます。
それは「美味しいお酒」という一言では表現しきれない、物語と余韻をまとった一本。
まるで舞台の一幕が終わったあと、拍手が鳴り止んだあとの静けさのように。
その酒を味わう時間は、日々の喧騒から離れた、心を整えるひとときになります。
佐賀県鹿島市の馬場酒造場が届ける能古見は、日常に寄り添いながらも、ときに特別な瞬間を演出してくれる存在。
地元で手に入れるのはもちろん、通販や酒屋でも購入可能です。
ぜひ一度、舞台の幕を引くような一杯を体験してみてください。
また、季節と酒の関係については「夏祭りや花火大会に日本酒はアリ?冷酒・ロックで楽しむ屋外イベントの極意」でも詳しく取り上げています。