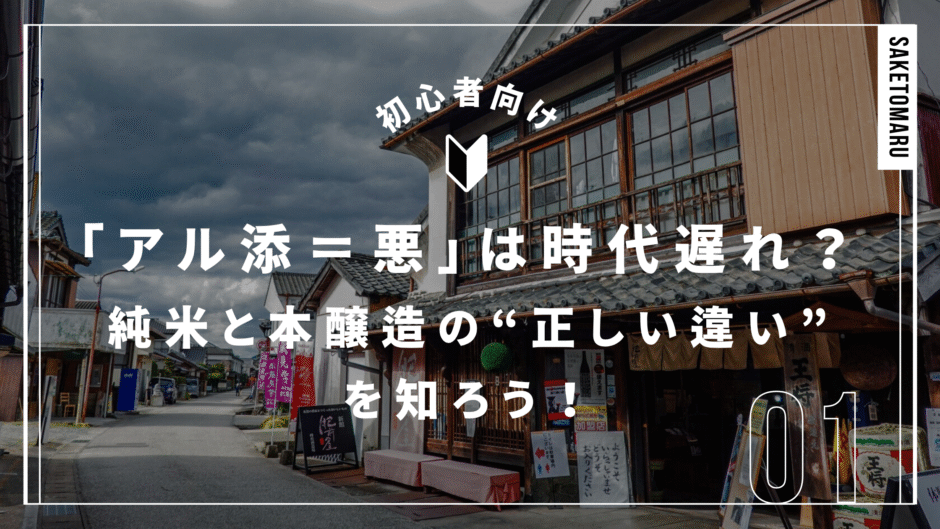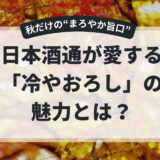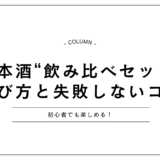「純米酒はいいお酒」「アル添(アルコール添加)は体に悪い」──そんなイメージ、持っていませんか?
最近では「無添加」「自然派」といった言葉が注目を集めていることもあり、日本酒の世界でも“アル添=悪”のように語られる場面が増えています。しかし、それは本当に正しいのでしょうか?
「純米酒」と「本醸造酒」の違いは、単なる“添加の有無”だけではありません。じつは、製造方法や味わいの特徴、そして酒造りの哲学にまで関わる奥深いテーマなのです。
この記事では、日本酒の「アル添」に対する誤解をほどきながら、純米酒と本醸造酒の違いを正しく、そして丁寧に解説していきます。
あなたがこれから日本酒をもっと楽しむために――知っておきたい、真実の一杯の選び方へご案内します。
日本酒にはさまざまな分類がありますが、最も大きな分かれ目のひとつが「純米酒」か「本醸造酒」かという点です。
純米酒とは?
純米酒とは「米、米麹、水」だけを原材料とした日本酒です。酒造アルコールを一切加えず、米の旨みやコクを生かす造りが特徴で、自然な味わいとどっしりしたボディ感を楽しめます。ラベルに「純米」とあるものはすべて、アル添されていないということになります。
種類には「純米」「純米吟醸」「純米大吟醸」などがありますが、いずれも醸造アルコールは使っていません。
本醸造酒とは?
一方、本醸造酒とは「米、米麹、水」に加えて「醸造アルコール(※)」を適量添加した日本酒です。添加といっても、目的は“かさ増し”ではありません。
添加の目的には:
- 発酵の安定化
- 味わいの軽快化
- 香りの引き出し
などがあり、味わいや香りをより整えるための「技術のひとつ」として行われています。
※使用される醸造アルコールは、基本的にサトウキビなどを原料とした高純度アルコール。無味無臭で、雑味はありません。
おすすめ記事: 「自分の酒量、わかってる?」──日本酒好きが陥りやすい“限界”との付き合い方
「アル添は体に悪い」「純米酒こそ正義」といった声を耳にすることもありますが、これは日本酒に対する大きな誤解のひとつです。そもそも“アル添(=醸造アルコールの添加)”は、品質を高めるために導入されたれっきとした醸造技術です。
なぜ“悪”だと思われがちなのか?
戦後の米不足の時代、一部のメーカーが質の悪い酒を大量生産するために、糖類や酸味料を加えた「三増酒」を販売しました。これが原因で「アル添=安酒」「身体に悪い」というイメージが定着してしまったのです。
しかし現在の本醸造酒や吟醸酒に使われる醸造アルコールは、酒質の調整や香りの引き立てのために極めて少量使われており、まったくの別物です。
アル添のメリットとは?
- 香りをクリアに整える:特に吟醸系の香り高いお酒では、余分な香りを抑え、フルーティーさを引き出す助けになります。
- 雑味を抑えられる:アルコール添加によって、酒中の微量成分がクリアにまとまり、後味がすっきりします。
- 熟成をコントロールできる:保存中の変化が穏やかになるため、安定した品質が保たれます。
つまり、アル添は「ズル」ではなく「プロの技」。純米酒と本醸造酒は、それぞれの良さを持った別物であり、目的や料理との相性に応じて選ぶことが大切なのです。
日本酒を選ぶとき、「とりあえず純米を選んでおけば安心」という方は少なくありません。確かに純米酒は、米と米麹だけで造られるというシンプルさゆえに、素材や造り手の意志がダイレクトに伝わるお酒です。しかし、“純米”であることが絶対ではありません。
むしろ、飲むシーンによっては本醸造酒やアル添された吟醸酒の方が、相性が良いことも多々あります。
食中酒として楽しむなら?
和食全般に合うのは、軽快でキレのある酒質の本醸造酒。たとえば焼き魚や煮物、揚げ物など、脂や塩気のある料理には、純米酒よりもすっきり系の本醸造のほうが“邪魔をしない”うまさを発揮します。
香りを楽しみたいなら?
華やかな吟醸香を楽しみたい場合は、アル添された吟醸酒・大吟醸酒がベスト。純米吟醸よりも香りが澄んでいることが多く、ワイングラスに注げばまるで白ワインのようなエレガントな香気が立ち上ります。
燗で楽しむなら?
実は、燗酒との相性が良いのも本醸造酒。温めることで米の旨味がまろやかに広がり、アルコールによる辛口感がキレとして心地よく残るため、冬の晩酌にもピッタリです。
かつて「アル添(アルコール添加)された日本酒は安酒」というイメージが広く浸透していました。しかし、これはもはや過去の話。現代の日本酒市場では、アル添は単なるコストカット手法ではなく、味や香りの“設計技術”として極めて重要な役割を担っています。
とくに、高級なアル添酒の世界を覗いてみると、その品質の高さに驚かされるはずです。
有名酒蔵が誇る“技アリ”の一本たち
たとえば、全国的に人気の「十四代」や「黒龍」の大吟醸・本醸造シリーズ。これらは米を極限まで磨いた上で、香りや味のバランスを追求するために、あえて醸造アルコールを添加しています。
アル添によって得られる利点は以下の通り:
- 香りをクリアに引き出す
- 口当たりをなめらかに整える
- キレのある余韻を生む
これらはすべて、アル添だからこそ実現できる酒質です。つまり、高級酒におけるアル添は“調味料”ではなく、“味の設計”そのものなのです。
アル添があるからこそ生まれる“香味の頂点”
アル添酒の代表格である大吟醸酒では、華やかな香りが非常に大切な要素。純米大吟醸ではどうしても香りが重たくなったり、発酵管理が難しくなったりするケースもあります。
その点、アル添を適切に加えることで:
- 香り成分を逃さず抽出
- 甘みと酸味のバランスを調整
- 酒質を“軽やかで美しい”方向に導ける
こうした特徴は、純米酒では得られないアル添ならではの魅力といえるでしょう。
「アル添=安酒」「純米=高級酒」という価値観は、すでに過去のものになりつつあります。確かに昭和期の量産型アル添酒には粗悪なものもありましたが、現在の日本酒業界ではアル添は技術であり、表現の手段です。
本醸造や吟醸、大吟醸の世界では、香り・口当たり・キレを計算して造られる“設計された味”が多く見られます。それは、米と酵母とアルコールという素材の特性を熟知した造り手による、職人技の結晶です。
一方で、純米酒にも確かな魅力があります。自然な旨味や酸味、濃醇な味わいを楽しみたい人にはうってつけでしょう。つまり、アル添と純米は“好み”で選ぶべきジャンルであり、優劣では測れないものです。
今こそ、ラベルの先にある「造り手の哲学」を感じよう
日本酒の楽しみは、ラベルに書かれたスペックだけでは語り尽くせません。「純米だから身体にいい」「アル添だから手抜き」そんな単純な見方ではなく、その酒をどう仕上げたか、何を狙って造ったかに目を向けてみましょう。
ときに雑味を減らし、ときに香りを高め、ときにキレを加える。すべては「美味しい」を届けるための工夫。その中に日本酒の奥深さと、造り手の情熱が宿っているのです。
あなたの「美味しい」は、どこにある?
純米酒も、アル添酒も、そして発泡酒や熟成酒までも──
今の時代は、日本酒の選択肢がかつてないほど広がっています。
大切なのは、「どんなスペックか」ではなく、「自分にとってどれが心地よいか」。
今日の記事を通して、“純米かアル添か”という二元論を超えて、あなたの日本酒選びがもっと自由で楽しいものになることを願っています。