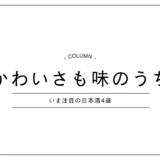日本で稲作が伝来した弥生時代以降、米を原料とする発酵飲料の可能性が語られ始める。酒の起源には諸説あり、縄文時代に果実酒・植物酒が存在したという報告もあるが、米酒としては弥生以降に発達したと考えられている。
古代の神事では「口噛み酒(くちかみざけ)」という方法が伝承されており、蒸した米を人が噛んで唾液中の酵素を使い糖化させ、自然発酵させるスタイルだとされる。藤原期・奈良の風土記にも記述が残る。だが、これがすべての日本酒につながる“元祖”という証拠はない。
奈良時代には中国由来の麹技術が導入され、宮廷内に「造酒司(みきのつかさ)」という役所が設けられ、酒が国家管理下に置かれる体制が生まれた。麹を使うことで糖化・発酵が安定化し、酒づくりの技術基盤が整備されていく。
室町・戦国時代には酒屋が現れ、酒が商品化され始める。「段仕込み」「諸白造り」技法の確立や火入れの始まりなど、より洗練された技術が採用され、品質の安定と流通の拡大が進む。
江戸時代、京都付近。関西地方の酒どころが「下り酒」として江戸に供給されるようになり、ブランド化が進む。冬に醸す「寒造り」が普及し、杜氏制度も整い、酒造技術と流通網の進歩が酒文化を大規模に支えるようになる。
明治時代には酒税制度、酒造免許制など制度化が進む。醸造試験所の設立や温度計・精米機など技術導入が進み、品質管理が向上。昭和期には三増酒などの増量技術も登場しつつ、特定名称酒制度への動きが出始める。

戦後は米不足や混乱期を経て、1960〜70年代には清酒の需要がピークを迎える。その後消費が減少する中、1990年代以降クラフト酒や小蔵の挑戦が目立つようになる。さらに地理的表示(GI)制度が導入され、日本酒の産地と品質を守る枠組みが整備される。
日本酒の呼称「日本酒」は、国産米を使い国内で醸造された清酒のみが使用できるようになった。2015年に「日本酒」が地理的表示(GI)に指定され、産地名の表示やブランド価値の保護が強化された。現在、全国の複数地域でGI指定がなされている。
日本酒は、古代の神事酒から始まり、麹・酵母・技術・制度を経て、現代ではクラフト性や地域性を重視する新たな局面にある。歴史を知れば、日本酒を飲むときの見方が変わる。伝統を守りつつ多様性を許容する、日本酒の未来は今も動いている。