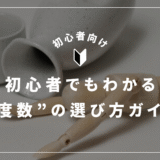日本酒の中でも、見た目にもインパクトがある“白く濁った”お酒──それが「にごり酒」です。
「なんとなく甘そう」「初心者向け?」そんなイメージを持たれがちですが、実は種類も幅広く、通好みの1本も多く存在します。
この記事では、にごり酒の基本から味の特徴、初心者でも楽しめる選び方、さらにはおすすめの飲み方までを丁寧に解説。
「にごり酒ってなに?」「気になってるけど買ったことがない…」という方でも、読めば今すぐ飲んでみたくなる、そんな魅力に迫ります。
にごり酒は「もろみ」を残したまま瓶詰めする
にごり酒とは、日本酒を搾った際に「もろみ」と呼ばれる酒粕の一部を、あえて残したまま瓶詰めしたお酒のことです。
通常の日本酒は、搾ったあとに細かく濾過されて透明になりますが、にごり酒ではその濾過工程が簡略化されているため、白く濁った見た目になります。
この“にごり”部分には、米や麹由来の風味や旨味が残されており、まさに「お米を飲む」ような濃厚さが味わえるのが魅力。
見た目のインパクトだけでなく、日本酒本来の素材感を存分に感じられる、まさに“飲むお米のデザート”ともいえる存在です。
清酒とはどう違う?うすにごり・どぶろくとの違いも解説
よく混同されるのが「どぶろく」や「うすにごり」との違い。
- 清酒(ふつうの日本酒):もろみを完全に濾して透明な状態
- にごり酒:粗く濾して、もろみ成分を一部残した白濁酒
- うすにごり:透明な酒に、ほんのり濁りが入ったバランスタイプ
- どぶろく:ほぼ無濾過。もろみを丸ごと残したトロトロの発酵酒(酒税法上、別カテゴリー)
とくに「どぶろく」は製造免許が異なるため、商品として出回ることが少なく、にごり酒とは別物です。
うすにごりは、「にごり酒に挑戦したいけど、濃すぎるのは不安」という方にぴったりな“入門編”ともいえるタイプです。
甘口が多い?実は辛口タイプもある
にごり酒というと、「甘くてまろやか」というイメージを持たれることが多いです。
実際、甘口タイプのにごり酒は豊富で、口当たりが柔らかく、日本酒初心者やお酒に弱い方にも飲みやすいものが多く流通しています。
しかし、実は「辛口タイプのにごり酒」も存在しています。
例えば、発泡性がありながらもキレのある味わいを持つスパークリングにごり酒や、後味をすっきりと仕上げた食中酒向けの辛口にごり酒など、ラインナップは豊富。
甘さ一辺倒ではなく、酒蔵ごとの個性が色濃く反映されるため、「にごり=甘い」という思い込みを一度リセットしてみると、楽しみ方の幅が一気に広がります。
炭酸感・舌触り・香りの多様性
にごり酒の魅力は、何といってもその複雑なテクスチャーと香りです。
濁っていることで、通常の清酒よりも「米由来のふくよかさ」が強く感じられます。
さらに、
- 舌にふわっと残るトロみ
- 炭酸ガス由来のシュワっと感(瓶内二次発酵タイプ)
- 酵母の香りや、ほのかなヨーグルト様の酸味
など、五感を使って味わえる楽しさがあります。
まるでデザートワインのように甘美でリッチな風味を持つものもあれば、すっきりシャープに仕上げた“意外性のある”にごり酒もあり、奥が深いジャンルです。
“最初の一杯”にぴったりなにごり酒の選び方

にごり酒は種類が豊富なだけに、初めて選ぶ際は迷ってしまいがちです。
初心者にとって重要なのは、「甘すぎない」「クセが強すぎない」「アルコール度数が高すぎない」こと。
そのうえで、口当たりが柔らかく、香りが穏やかな銘柄を選ぶと失敗しにくいです。
特におすすめしたいのは「うすにごり」タイプ。
にごりの良さはそのままに、口当たりや見た目が軽やかなので、最初の1本にぴったりです。
また、アルコール度数が13〜14度程度のライトなタイプを選ぶと、飲み疲れしにくく安心です。
初心者に人気のにごり酒銘柄
以下は、日本酒ビギナーからも人気が高く、飲みやすさで評判のあるにごり酒です:
| 銘柄名 | 特徴 | アルコール度数 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 八海山 発泡にごり酒(八海醸造) | シャンパンのような泡立ちと爽快感|辛口寄りの発泡にごり | 約15% | 発泡タイプ |
| 桃川 にごり酒(白鶴酒造) | スッキリした甘みとバランスの良さ|梅の風味も感じられる | 15% | 標準的にごり酒 |
| 白川郷 純米にごり酒(三輪酒造) | 濃厚で米の旨味たっぷり|初心者は少量から | 14.5% | 濃厚タイプ |
| 竹鶴 純米にごり酒(竹鶴酒造) | にごり酒では珍しい辛口|和食とも好相性 | 約14% | 辛口タイプ |
| 会津ほまれ にごり酒(会津ほまれ酒造) | 定番で安定感あり、価格もリーズナブル|日常使いに最適 | 15% | スタンダード系 |
どれもスーパーや酒販店、ネットショップで入手可能で、価格帯も1,000円台〜3,000円前後と手が届きやすいのも魅力です。
冷やしてすっきり、ぬる燗でコク深く
にごり酒は温度によって驚くほど味わいが変わるお酒です。
- 冷やして(冷酒):発泡タイプやフルーティーなにごり酒には最適。甘みと炭酸感が引き立ち、爽快で飲みやすい。
- 室温〜常温:舌触りとコクを楽しめるスタイル。ほんのり甘味を感じながら、にごりの風味を味わえます。
- ぬる燗(約40℃):糖分や酵母由来の旨味が立ち上がり、まろやかさと深みが増す温め方。甘めの煮物や鍋料理と好相性です。
それぞれ温度帯で味わいが変化するため、自宅で複数の楽しみ方を試すのもにごり酒の魅力です。
炭酸割り・牛乳割りなど意外なアレンジもあり
にごり酒はアレンジしやすさも魅力の一つ。特に若者や女性には、以下の飲み方が人気です。
- 炭酸水で割る:発泡にごり酒やライトなにごりで作る日本酒ハイボール風。レモンやハーブを添えると見た目もおしゃれ。
- トニックウォーター割り:炭酸の苦味とにごりの甘みが絶妙にマリアージュ。前菜やアペタイザーとの相性も◎
- 牛乳割り:クリーミーなコクがプラスされ、まるでカフェドリンクのようなデザート酒に。
- フルーツスライス(柑橘・リンゴなど)を浮かべて:香りと酸味が加わり、爽やかさと見た目の華やかさがプラスされます。
このように自由にカスタムできる点も、にごり酒の面白さです。
発泡タイプは要注意!開栓時の“吹きこぼれ”に注意
にごり酒の中には、瓶内発酵を続けるタイプがあり、開けた瞬間に中身が勢いよく噴き出すことがあります。
とくに発泡系や生酒タイプは以下のような注意が必要です。
- 冷蔵庫でしっかり冷やしてから開ける(ガス圧を抑えるため)
- 開栓前に瓶を振らない
- キャップをゆっくり開け、ガスを少しずつ逃がす
一気に開けると服や壁が酒まみれになる可能性も…。
特にプレゼントや飲食店で提供する際は要注意です。
保存方法は「冷蔵」が基本!
にごり酒は酵母や糖分、アミノ酸が豊富なため、温度変化や光に弱く劣化しやすい酒です。
保存時のポイントは以下の通り:
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| 冷蔵庫で保管(5〜10℃) | 発酵の進行を抑え、味の変化を防ぐ |
| 日光・蛍光灯を避ける | 光で劣化しやすい成分が含まれるため |
| 開栓後は1週間以内に飲みきる | 酸化が進み、風味が大きく変わるため |
瓶の中に残る酵母が生きている場合、時間と共に風味が変化していくため、開けたらできるだけ早めに楽しむのがおすすめです。
飲みやすさと個性が、日本酒のイメージを変える
にごり酒は、その白く濁った見た目と、口当たりのやさしさで、日本酒に苦手意識のある人にもスッと入ってくるお酒です。
- 甘みやフルーティーさ
- 微発泡の爽快感
- クリーミーな舌触り
これらの特徴は、ワインやカクテルが好きな層にも受け入れられやすく、「あ、日本酒ってこういうのもあるんだ」と、これまでにない体験を届けてくれます。
選び方に迷ったら「うすにごり」から
初めてにごり酒を試すなら、濃厚なタイプよりも「うすにごり」や「スパークリング系」がおすすめ。
後味が軽やかで、飲みやすく、和洋問わず食事にも合わせやすいのが特徴です。
近年では各酒蔵が趣向を凝らしたにごり酒を出しており、ラベルデザインも可愛いものが多く、ギフトやパーティーにもぴったり。
にごり酒を入口に、日本酒の世界へ一歩踏み出してみてください。