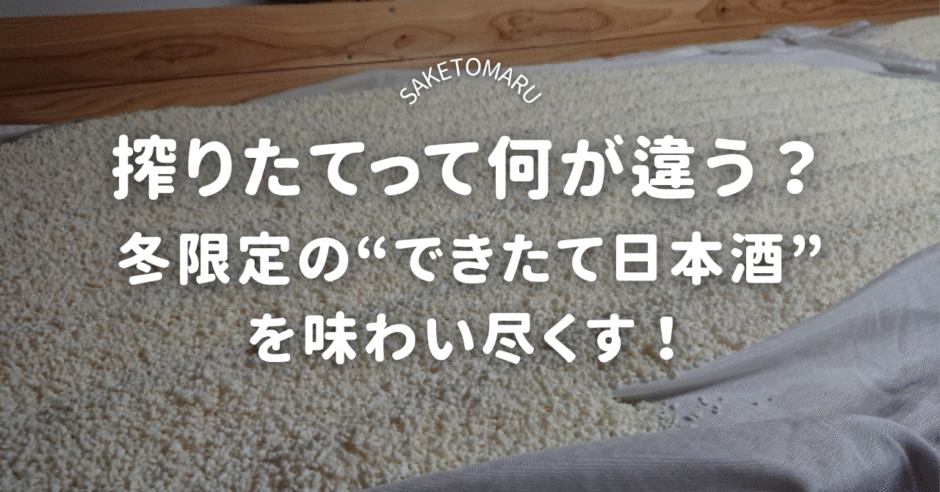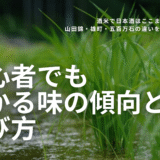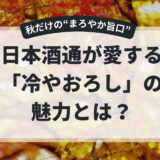「しぼりたての日本酒、入ってます!」
──そんな言葉を酒屋や居酒屋で見かけたことはありませんか?とくに冬から春にかけての季節、限定酒として並ぶことが多い「搾りたて日本酒」。でも、そもそも“搾りたて”とはどんな状態を指すのでしょうか?
同じように見える日本酒でも、ラベルに「搾りたて」や「しぼりたて」「生原酒」などと書かれているものは、香りや味わい、鮮度がまったく異なります。実は、これらの違いを知ることで、自分にぴったりの“美味しい1本”に出会える可能性がぐっと広がるのです。
この記事では、「搾りたて日本酒」の意味や他のタイプとの違い、味わいの特徴、そしておすすめの銘柄や楽しみ方まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
「搾りたて」とは、その名のとおり日本酒を“搾ったばかり”の状態を指しますが、実際にはもう少し深い意味があります。
日本酒は、醪(もろみ)と呼ばれる発酵途中の液体を「上槽(じょうそう)」という工程で、酒と酒粕に分けることで完成します。この“上槽”こそが「搾る」工程であり、「搾りたて」はこの瞬間に得られた新酒を指すのです。
「搾り=上槽」の意味とは?
日本酒の仕込みは、米・水・麹・酵母をタンクに入れて数週間〜1か月発酵させる「醪造り」から始まります。その後、いよいよ発酵がピークを越えたタイミングで、醪を搾って液体(清酒)と固形物(酒粕)に分けます。これを「上槽」と呼びます。
この上槽直後の酒は、非常にフレッシュでガス感があり、酵母の生命力や米の香りが強く残っています。
「搾りたて=瓶詰め直後」ではない?
実は「搾りたて=すぐ瓶詰めされた酒」と誤解されがちですが、実際には少し異なる場合もあります。たとえば、
- 搾った直後にすぐ瓶詰めされるもの(生原酒など)
- 搾ってすぐは貯蔵し、あとから瓶詰めされるもの(火入れ後でも「しぼりたて」の風味を重視する)
というように、蔵によっては少し時間をおいてから出荷する場合もあります。ただし、いずれも「しぼった時期が近い=旬の味わいが残っている」ことは共通しています。
「新酒」や「生酒」とは違うの?

「新酒」も「搾りたて」と近い概念ですが、以下のような違いがあります。
| 用語 | 定義・意味 |
|---|---|
| 搾りたて | 上槽直後のフレッシュな状態を表す |
| 新酒 | その年度に搾られた酒(11〜翌3月頃) |
| 生酒 | 火入れ(加熱処理)をしていない酒 |
| 生原酒 | 火入れ・加水のどちらも行っていない濃い酒 |
つまり「搾りたての新酒」「搾りたての生原酒」というように、複合的に使われるケースも多いのです。
おすすめ記事: “生原酒”ってどう保存する?──要冷蔵・賞味期限・劣化リスクまで完全ガイド
搾りたての日本酒には、通常の市販酒とは一線を画す「鮮烈な個性」があります。
その魅力は主に、【味わい】【香り】【アルコール感】の3つに分けられます。
味わい:荒々しさと米の旨みがダイレクトに
搾りたての酒はまだ“落ち着いていない”状態です。
よく言えば若々しく、悪く言えば「粗さ」があります。ですがこの粗さこそが魅力。
熟成が進んだ酒にはない、フレッシュで力強い味わいが口いっぱいに広がります。
米の旨味がはっきりと感じられ、酸味や甘味も立体的で、飲みごたえがあります。
「洗練された」よりも「生命力がある」味わいを楽しみたい方には、まさにうってつけです。
香り:酵母由来のフルーティーなアロマ
しぼりたての酒は、酵母が発酵中に生み出したエステル系の香り(リンゴやバナナのような香り)が残っています。
火入れしていない生酒であれば、さらにその香りはフレッシュなまま瓶に閉じ込められています。
とくに「吟醸系のしぼりたて」は、華やかな香りが前面に出ることが多く、香り重視の方にはたまらない仕上がりです。
アルコール感:やや強めに感じる“飲みごたえ”
搾りたての日本酒は、多くの場合「原酒(加水していない酒)」であるため、アルコール度数が高め(16〜18度)です。
それにより、同じ量を飲んでも飲みごたえがあり、後口にしっかりとした熱感を残します。
ただし、搾りたて=濃厚というわけではなく、意外とスッと消える余韻の酒も多く存在します。
「厚みがあるのにキレがある」──そんな矛盾を感じさせるのも、搾りたてならではの魅力です。
「しぼりたて」と一口に言っても、ラベルに記される表記や製法の違いによって、その酒がもつ特徴は大きく変わります。ここではよく目にする表示やその意味を、初心者にも分かりやすく整理していきましょう。
生原酒(なまげんしゅ)
最もパンチのある“しぼりたて”の代表格です。
「生」=火入れをしていない、「原酒」=加水をしていない、という意味。
つまり、しぼったそのままの酒が瓶詰めされているということで、フレッシュさ・濃厚さ・香りの三拍子がそろっています。
- 味:力強く濃密。荒々しさが魅力。
- 香り:酵母の香りが際立つ。
- 注意点:要冷蔵。保存状態に気をつけたい。
しぼりたて生酒
火入れはしていないが、加水はされているタイプ。
フレッシュさは残しつつ、やや飲みやすく整えられているのが特徴です。
生原酒よりも軽やかな口当たりが多く、アルコール感も比較的まろやか。
- 味:ピュアで透明感のある仕上がり。
- 香り:フルーティーで華やか。
- 飲みやすさ:原酒より一歩やさしい印象。
直汲み(じかぐみ)
発酵タンクから搾った酒を、空気にほとんど触れさせずにそのまま瓶に詰める手法。
炭酸ガスが残っているため、微発泡のような舌ざわりを楽しめることも。
- 味:爽快でシャープ。
- 香り:香りよりも清涼感が際立つ。
- 特徴:冷やしてロックやソーダ割りにも向く。
あらばしり
搾りの工程で最初に出てくる部分の酒。
“荒ばしり”と書くこともあり、読んで字のごとく、味わいが荒々しく、フレッシュで勢いのある味が特徴です。
- 味:ドライで野性的。まさに“初々しい”。
- 香り:若く、ややアルコール感強め。
- 飲み方:冷酒またはロックがおすすめ。
「しぼりたて」の日本酒は、その名の通り“できたてホヤホヤ”のフレッシュさが最大の魅力。しかし、そのフレッシュさは非常にデリケートでもあります。ここでは、搾りたて日本酒の美味しさを損なわないための保存と楽しみ方のポイントを解説します。
保存は“必ず冷蔵”が基本
搾りたては「生酒」や「生原酒」であることが多く、火入れ(加熱殺菌)されていないため、非常に繊細です。常温に置くと、急激な温度変化や日光によって劣化してしまう可能性があります。
- 冷蔵庫(できれば4〜6℃)で保管
- 日光を避け、できれば新聞紙などで遮光
- 開封後はできるだけ早く飲み切る(2〜3日以内が理想)
とくに「直汲み」や「あらばしり」は炭酸が残っていることもあり、時間が経つと風味が変わりやすいので要注意です。
開けたての「ガス感」を楽しむなら早めに
搾りたての中には、ほんのり微炭酸が残るタイプもあります。この“ピチピチ感”は、開栓直後がもっとも感じやすい要素。数日経つと抜けてしまうため、開けたらその日のうちに味わうのがベストです。
また、酸化が進む前の若々しい香りや味わいを楽しむのも、開封当初の特権です。
おすすめの温度帯と飲み方
搾りたて日本酒の魅力を引き出すには、温度とグラスにも少し気を配ってみましょう。
| 温度帯 | 特徴 |
|---|---|
| 5〜10℃(冷酒) | フレッシュな香りとキレのある味わいが際立つ |
| 10〜15℃(涼冷え) | 甘みや旨味のバランスがとれ、やや穏やかな印象に |
| 15℃以上(常温) | 生原酒など一部で甘みや膨らみが楽しめるが、雑味も出やすい |
- フルーティーなタイプには「ワイングラス」型
- ガス感を活かしたいなら「細身のシャンパングラス」もおすすめ
おすすめのペアリング(食事)

搾りたてのフレッシュでやや刺激的な味わいには、同じく爽やかで脂が少ない料理が合います。
- 白身魚の刺身(鯛・ヒラメなど)
- 生牡蠣・カルパッチョ
- 冷製の前菜(蒸し鶏・おひたし)
- 塩味ベースの鍋(豆乳鍋など)
「食中酒」としても重すぎず、料理の風味を邪魔しないところも魅力です。
日本酒のラベルに「しぼりたて」と書かれているだけで、なんとなく惹かれる──そんな方も多いはず。でも、実際に買うとなると「どれを選べばいいの?」「何を基準に選べば失敗しない?」と迷ってしまうことも。
ここでは、初心者でも安心して“しぼりたて”日本酒を選べるように、注目すべきポイントを整理しておきましょう。
タイプ別の表記を知っておこう
「しぼりたて」といっても、その種類はさまざま。ラベルには多くの情報が載っているので、どの表記がどんなタイプかをざっくり把握しておくと選びやすくなります。
| 表記 | 特徴 |
|---|---|
| 生酒・生原酒 | 火入れを一切していない。冷蔵保存必須でフレッシュ感MAX |
| 直汲み | 搾った酒を空気に触れさせずそのまま瓶詰め。ガス感あり |
| あらばしり | 一番最初に出てくる酒。荒々しさと若々しい香り |
| 中取り・中汲み | 酒質のバランスが良く、滑らかで飲みやすい |
| 無濾過 | フィルターでこさずに瓶詰め。旨味たっぷりで濃厚 |
特に「生酒 × 無濾過 × 直汲み」など複数の要素が重なると、かなりパンチのある仕上がりになります。初心者なら「中取り」や「無濾過生原酒」を最初の一歩に選ぶと、バランスよく楽しめるでしょう。
アルコール度数にも注目
しぼりたてはアルコール度数が高い傾向にあります。原酒だと17〜18度のものも多く、飲み口の軽さと裏腹に酔いやすいのが特徴です。
初心者が一人で飲む場合は「15〜16度」くらいがちょうどよく、味の濃さと酔い具合のバランスが取れます。
購入時は「出荷日」にも注意
搾りたては基本的に“フレッシュ命”の酒。購入時にはラベルや販売ページにある「出荷日」「瓶詰日」「製造年月日」をチェックし、なるべく新しいものを選ぶとベストです。
オンラインで買うときは、「出荷直後」や「季節限定」と明記されているかも判断材料にしましょう。
地元銘柄に注目すると“当たり”に出会えることも
全国の有名銘柄も良いですが、酒蔵が近い地域の“地元搾りたて”は新鮮さが段違い。移動距離が少ないぶん、コンディションの良い状態で店頭に並ぶことが多いです。
地元酒屋や蔵元直営店をのぞいてみると、全国には出回らない「その土地の味わい」に出会えるかもしれません。
「しぼりたて日本酒」は、ただのラベル表記ではありません。それは、酒蔵が仕込みの“旬”に心を込めて送り出す、季節の贈り物のような存在です。
フレッシュでピュアな飲み口、果実のような香り、微発泡の刺激──しぼりたての魅力は、他の酒にはない“ライブ感”にあります。そして、その旬はとても短い。だからこそ、出会えた瞬間を大切にしたいのです。
飲み方の工夫や保存の注意点さえ押さえれば、初心者でもしぼりたての世界にしっかりと足を踏み入れることができます。たった一本の日本酒が、季節を感じさせてくれる。それが“しぼりたて”の真骨頂。
冷やしてキュッと、ぬる燗でじんわり。
ぜひ、自分だけの「搾りたてスタイル」を見つけてみてください。
関連サイト: 24-25冬 新酒生酒 しぼりたて