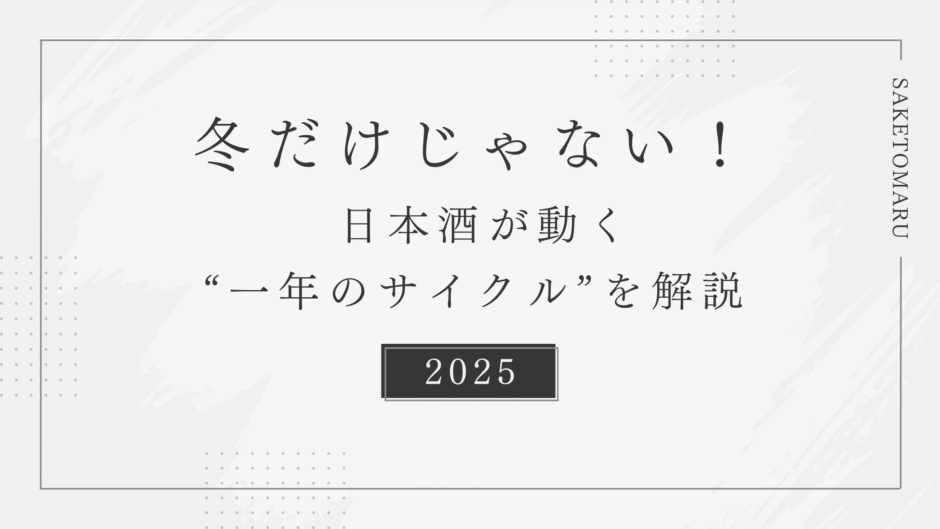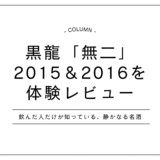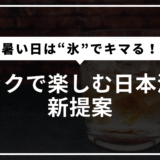コンビニやスーパーで一年中見かける日本酒。でも実は、日本酒には“造る時期”があることをご存じでしょうか?「冬に仕込む」というのは、なんとなく聞いたことがあるかもしれません。でもなぜ冬?なぜ春でも夏でもなく“寒い季節”なのか。
この記事では、日本酒が造られる季節的な背景や、なぜ寒仕込みが伝統になっているのか、そして佐賀県鹿島市に根付く季節ごとの酒造りのリズムについて、丁寧にひも解いていきます。
日本酒の“酒造年度”とは?

日本酒の世界では、一般的な暦年(1月〜12月)とは異なり、「酒造年度(BY=Brewery Year)」という独自のカレンダーが使われています。これは7月1日から翌年6月30日までの1年間を1つの酒造年度として捉えるものです。
このカレンダーで見ると、多くの酒蔵が仕込みを開始するのは10月〜翌年3月。この半年間こそが、いわゆる“酒造りの季節”にあたります。
寒仕込みが基本となる理由
日本酒は「寒仕込み」が基本とされます。その理由は以下の通りです。
- 雑菌の繁殖を防げる:気温が低い冬場は雑菌の活動が鈍く、衛生管理がしやすい。
- 低温発酵が可能:発酵温度をコントロールしやすく、繊細な香りや旨みを引き出せる。
- 米の品質が安定:秋に収穫された新米を使用できるため、米の状態が良い。
つまり冬は、自然条件が酒造りにもっとも適した季節なんです。
10月から始まる“仕込み準備”
佐賀県鹿島市の酒蔵も、例外ではなくこの寒仕込みを基本としています。鹿島の蔵元たちは、10月ごろから次第に仕込みの準備に入ります。
- タンクの洗浄
- 精米された米の受け入れ
- 酵母や麹の準備
- 仕込み水の管理 など
この時期になると、蔵にはピリッとした空気が漂いはじめます。
11月〜2月はピークシーズン
実際に“酒が生まれる”のは、11月から2月にかけて。この時期は、地元でも「蔵が動き始めたな」と感じるほど、活気に満ちあふれます。
「搾りたて新酒」を12月〜1月頃に限定販売する蔵も多く、これを楽しみにしている地元ファンも多い。
春(3月〜5月):仕込みの終わりと瓶詰め・出荷のピーク

冬に仕込んだ酒が順次発酵を終え、春になると瓶詰め作業が本格化します。この時期は、特に「しぼりたて」や「生酒」の出荷がピークを迎え、出荷現場は非常に慌ただしくなります。
さらに春は、新年度の始まりでもあり、贈答需要や花見需要に合わせたプロモーションも増える季節です。各蔵元は春限定ラベルやギフト用の包装など、商品開発にも力を入れる時期となります。
また、酒蔵によっては春に蔵開きイベントを開催し、地域住民や観光客に向けた試飲会・見学会なども行います。これにより、地元とのつながりを深め、新しいファン層の開拓につなげているのです。
夏(6月〜8月):熟成期間と設備のメンテナンス、秋酒の準備

日本酒業界にとって“夏は閑散期”と誤解されがちですが、実は大切な準備期間でもあります。気温が高くなるこの季節は、基本的に日本酒の仕込みは行いません。
その代わり、冬に搾った酒を熟成させるための温度管理が非常に重要になってきます。熟成タンクや瓶貯蔵の環境を整え、品質を維持するために日々の細かなチェックが欠かせません。
また、設備の点検・修繕や、次の仕込みに向けた資材の発注、麹室(こうじむろ)の清掃など、蔵人にとっては“整える”仕事が続く季節です。
一方で、秋に向けた「ひやおろし」や「秋あがり」といった熟成酒のラベルデザインや販促計画が練られるのもこのタイミングです。まさに“影の仕込み”が進む、静かだけど重要な期間です。
秋(9月〜11月):ひやおろしの出荷と冬の仕込みへの助走

夏を越して円熟味を帯びた酒は「ひやおろし」として出荷されます。加熱処理を春に1回だけ施し、その後は冷蔵・常温で静かに熟成されたひやおろしは、秋の味覚にぴったりと合うため、この時期の主役になります。
同時に、冬の仕込みに向けて原料米の調達や洗米・蒸し設備の再稼働準備が本格化します。特に近年は、酒米の品種改良が進んでおり、品種ごとに精米の適正や吸水率が異なるため、事前の調整が不可欠です。
また、蔵人が戻ってくる時期でもあり、新しいスタッフの研修や役割分担の確認など“人の再編成”も秋の重要な仕事です。
一部の小規模酒蔵では“通年仕込み”も増加
近年、設備の進化により、冷房完備の蔵では夏場でも仕込みが可能になりつつあります。特に小ロット多品種を展開するクラフト系の酒蔵では、年間を通じて仕込みを行うケースも。
ただし、冷却・衛生管理の手間が大きくなるため、採算や効率の面では課題も多く、あくまで特殊なスタイルとして浸透しつつあります。
冬仕込みの“価値”は失われていない
通年仕込みが可能になっても、冬仕込みが持つ意味は変わりません。厳しい寒さの中で雑菌の繁殖を抑え、ゆっくりと発酵させることで、味に奥行きと透明感が生まれる──この醍醐味は、現代でもなお支持されています。
そのため「純米大吟醸」や「無濾過生原酒」などの高級酒・限定酒は、いまでも冬場に仕込まれることが一般的です。
日本酒は仕込む時期だけでなく、飲むタイミングでも味の印象が変わるお酒です。たとえば同じ銘柄でも、「しぼりたて」と「秋あがり」ではまったく別物のように感じられることもあります。
| 季節 | 特徴 | 楽しみ方 |
|---|---|---|
| 冬(12月〜2月) | しぼりたて・新酒 | フレッシュな酸味・香り。冷酒で。 |
| 春(3月〜5月) | 生酒・薄にごり | 若さを残しつつまろやか。常温〜冷酒で。 |
| 秋(9月〜10月) | ひやおろし・秋あがり | 熟成による深み。常温〜ぬる燗が◎。 |
| 通年 | 燗酒向け | 温度で味が変化。熱燗・ぬる燗を使い分けて。 |
冬の仕込みは日本酒の“核”であることは間違いありませんが、実は1年を通じて酒蔵は常に何かしらの準備や活動をしています。
「仕込みは冬」「熟成は夏」「出荷は春・秋」というように、自然のリズムに寄り添って生まれる日本酒。だからこそ私たちも、ただラベルを見るだけでなく、「この酒はいつ仕込まれたのか」「いまはどんな旬が楽しめるのか」に目を向けると、一本の酒に対する解像度がぐっと上がります。
鹿島を含む日本各地の蔵元が、それぞれの季節に合わせた手間と工夫を注いで仕込む一本。そんな背景を知った上で味わう日本酒は、きっと今まで以上に美味しく感じられるはずです。